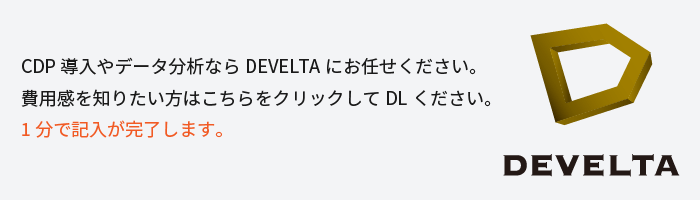デシル分析とは、各顧客からの購入金額を集計し、ランク分けする分析法です。
企業に蓄積されたデータを用いて顧客分析することにより、優良顧客を算出しマーケティングROIを高める効果を持っているデシル分析は特に注目されています。
企業がデータ活用を行う大きな目的は顧客を分析することであり、それによって購買予測を行うことが挙げられます。
データ活用による顧客分析が売り上げに寄与するとはいうものの、スマートフォンをはじめとするモバイルデバイスの普及やメディアの多様化によって顧客行動が多様化している近年。
単に顧客分析といっても、分析方法は無数に存在しています。
そんな数ある顧客分析の中でもデシル分析は、優良顧客を可視化することができるという点で、効果的なマーケティング施策を実行することができる顧客分析の1つなのです。
ここでは、マーケティング施策を最適化するためのデシル分析についてご紹介していきます。
さらに、デシル分析の目的や注目される背景、活用事例、類似性のあるRMF分析についても合わせて、紹介していきます。
この記事のポイント!
- デシル分析とは、各顧客からの購入金額を集計し、ランク分けする分析法。
- デシル分析を活用することで、高いROIを実現するマーケティング施策が可能。
- すでに顧客購入データを保有しているなら直ぐに実践可能。
- とくに継続課金型のビジネスモデルなら効果は大。
- RFM分析との違いは指数の数。シンプルに分析したいなら「デシル分析」がオススメ。
デシル分析とは

数ある顧客分析方法の中でも代表的な存在として知られるデシル分析。
デシルとはラテン語で「10分の1」の意味を持っており、それが語源となっていると言われています。
これは、簡単に言えば、顧客が今まで使った金額の合計、それをランク付けしたもの。
企業に蓄積された購買データを元にして、全ての顧客のうち、購入金額の高い順に10当分して算出します。
さらに、10区分したカテゴリを、それぞれランク付けすることで、購入比率や売上高の構成比を具体的に算出していきます。
これによって、そのランクに合わせたマーケティング施策を実現することが可能になります。
その結果、マーケティングROIの高い、企業の売り上げに直結する施策を実現するのです。
また、デシル分析はECサイトをはじめとするショップにおいて頻繁に活用されています。
というのも、ショップと顧客の関係を考えてみると購入金額が最も有用な指標だからです。
そのため、購買データを元に顧客分析を行うデシル分析と相性が良いのです。
デシル分析を始めるに前に
デシル分析は代表的な分析方法ですが、それより簡易的に顧客分析を行う方法に、特定の顧客を属性別に抽出する方法があります。
これは、一般的に店舗利用者やサイト利用者の電話番号やメールアドレスをはじめとする個人情報を元に顧客分析を行いマーケティングに活かす方法です。
たとえば、性別や年代で顧客カテゴライズします。
男性には男性用の商品ページを紹介していくメールマガジン。
高齢者には、シニア向けの商品カタログの郵送などのマーケティング施策が挙げられます。
これはデシル分析のように、購買データを活用するものではなく、登録データを活用するので、比較的容易に始めることができます。
また、これから事業を開始する方にとっては、まず取り組むべき施策といえるでしょう。
そして、こちらの属性別の抽出が済んだら、次に活用すべき顧客分析方法が購買データに基づいたデシル分析とも言えます。
こちらでは、すでに購入歴のある顧客がいる場合には適していると言えますので、すでに購買データを有している場合は、取り入れるべき施策といえます。
デシル分析の目的
デシル分析の大きな目的は企業の売り上げを伸ばすことと言えます。
デシル分析を行うことで、優良顧客をはじめとする顧客を階層的に認識することができるので、売り上げに貢献している顧客を顕在化することができるからです。
すると、貢献度の高い層に向けてマーケティングリソースを投下することができるので、マーケティングROIの高い適切なマーケティング施策を実現することができ費用対効果の向上が期待できます。
結局のところ、デシル分析の目的は売り上げ拡大を実現させるためといって相違ないのです。
これは他の分析手法の目的についても同様のことが言えます。
また、企業が存続する目的には社会貢献や自己実現などが挙げられますが、大きな要素は利潤追求です。
実際、企業は経営層や営業、マーケティングといったように分業されて形成されていますが、結果的にコンバージョン・マネタイズする箇所というのが重要になってきます。
つまり、コンバージョンやマネタイズを考える際の対象は顧客であり、重要なのは顧客分析なのです。
すると、企業にとって、デシル分析はもとより顧客分析は重視すべきポイントと言えます。
デシル分析が注目される背景
企業・顧客分析・デシル分析の目的は、売り上げの拡大が大きな割合を占めています。
そこで、近年のビジネスモデルの視点からデシル分析を見てみることにしましょう。
近年、続課金型のビジネスモデルを採用している企業が多くなってきました。
広告やCMでも継続課金型であったり、サブスクリプション、シェアリングエコノミーなど新しいビジネスに関する概念が登場し、それらが現在のビジネス界を席巻しているといっても過言ではないでしょう。
つまり、これらの概念は、以前のような切り売り型のビジネスではなく、継続的なビジネスモデルの隆盛を示唆させるものと言えます。
すると、デシル分析をはじめとする顧客データに基づく顧客分析は、今後さらに必要性を増していくことが予想されます。
実際、継続課金などのビジネスモデルを採用している企業の多くは、顧客分析を怠りません。
というのも、顧客視点で事業を考えることこそ売り上げ拡大に直結するからです。
デシル分析の他にも顧客に焦点をおいたRFM分析やカスタマージャーニーマップの作成、LTV(顧客生涯価値)がマーケティング施策として注目されていることからも、顧客視点の分析が重要視されていることがわかります。
RFM分析とは
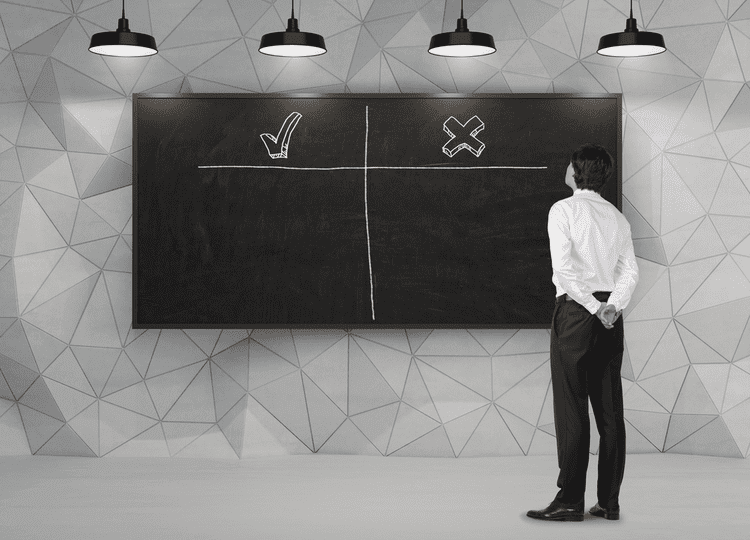
デシル分析と類似性のある顧客分析方法に、RFM分析があります。
これはRecency (直近の購入日)、Frequency(来店頻度)、Monetary (購入金額)の 3 つの指標で顧客をランク付けする手法です。
この指標に応じて顧客を階層的に並べ替え、カテゴライズすることでそのグループの性質を認識します。
そして、そのグループの性質に合わせたマーケティング施策を実践することでマーケティングROIの高い、つまり、売り上げ拡大に直結するデータを見極める顧客分析方法ともいえるでしょう。
また、RFM分析の場合は顧客分析のためにカテゴライズする際には、5つ程度に分類するのが一般的です。
- 優良顧客
- 非優良顧客
- 新規顧客
- 安定顧客
- 離反顧客
このようにデシル分析よりも顧客を具体的に細分化するので、ターゲットにより合致する施策を打てると言えます。
デシル分析とRFM分析の違い
デシル分析とRFM分析の大きな違いは、扱う指標の数です。
すでにご紹介してきたように、デシル分析で扱うのは基本的に購買データであり、合計金額のみという場合が一般的です。
一方で、RFM分析では直近の購入日、来店頻度、購入金額というように3つの指標を活用します。
そのため、分析方法がRFM分析の方が複雑で、時間と労力を有します。
しかし、それだけ効果的な顧客分析になることも間違いなく、実際にデシル分析よりも顧客を的確に捉えることができます。
そのため、これから顧客分析を始める場合にはRFM分析まで行う前提で、まずはデシル分析から始めることで無理なく、スムーズに顧客分析を可能にします。
まとめ
今回は、顧客分析を行い、マーケティングROIを高めるための分析方法である「デシル分析」についてご紹介してきました。
すでに多くの企業で取り入れられている方法で、実際にデシル分析を活用することで、成果を出している企業も無数に存在しています。
企業の限りあるリソースを効果的に投下し、利益に還元するためにも、デシル分析をはじめとする顧客分析は重要です。
さらに、今後継続課金型のビジネスモデルやサブスクリプションモデルの台頭が見込まれているように、顧客視点で事業を考えていくこともさらに重要視されていくでしょう。
結果的に、顧客分析を行うことで企業の売り上げ拡大に寄与すると期待できるので、早期に挿入を検討してみてはいかがでしょうか。