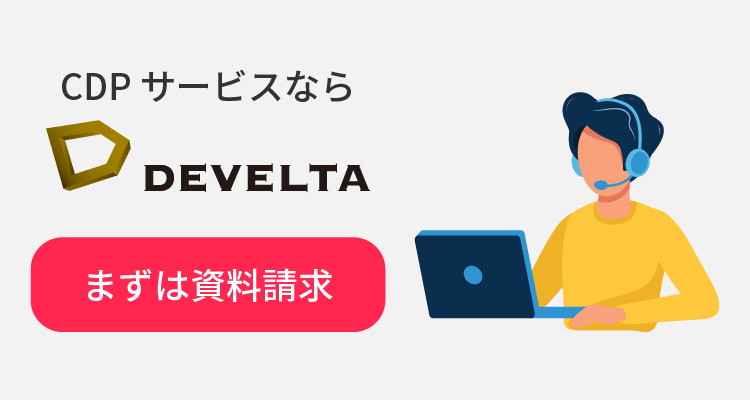導入
BIとは

BIという言葉を聞いたことがあるでしょうか?
BIはBusiness Intelligenceの略称で、企業内に蓄積された大量のデータから必要な情報を集約し、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うプロセスです。
BIツールは、組織のデータを収集し、データを分析し、データの可視化・BIダッシュボード・レポートを作成して、分析結果をビジネスユーザーに提供し、業務の意思決定や戦略立案に役立てます。
BIの機能
BIの機能は大きく分けてレポーティング・分析・プランニングの3つに分けられます。
レポーティング
レポーティングとは、企業に蓄積された大量のデータ(社内基幹システムデータ・外部システムデータなど)から情報を収集・集計し、一目で見やすい形式にして表示する機能です。
近年、企業のITビックデータ活用が進む中、経営の意思決定や予算編成などのシミュレーションに役立つとしてBIツールを導入する企業が増えています。
分析
データ分析は、あらゆるタイプのデータをモデル化・視覚化し、より良い意思決定をサポートするように設計された機能です。
これにより、ユーザーはトレンドの変化を発見し、問題を特定し、新たな洞察を得ることができます。
データソースに対して、OLAP分析やデータマイニング、プランニングなどの方法でデータを探索することができます。
OLAP分析(オンライン分析・多次元分析)
OLAPとはOnline Analytical Processingの略で、レポーティングツールで収集したデータを様々な視点から分析・処理し、問題点や解決策をするための方法です。
分析は、ドリルダウン・ダイシング・スライシングなどさまざまな視点で行われます。
ユーザーはOLAP分析により、トレンドを発見し、問題を特定し、新たな洞察を得ることができます。
データマイニング
データマイニングは、通常の分析とは違い大量のデータから新たな規則性を見つける方法です。
分析は、クラスター分析・マーケットバスケット分析・ロジティック回帰分析などさまざまな視点で行われます。
プランニング
プランニングは、これまで蓄積・分析したデータを元にさまざまな条件下でのシミュレーションを行い意思決定のサポートを行う方法です。
BIのメリット
BIツールを利用することで得られるメリットはたくさんあります。
まず、利用者の時間短縮に役立ちます。
これまで、データを活用する場合は必要な情報を見つけるために山のようなデータをかき分けて多くの時間を浪費しなければなりませんでした。
しかし、BIツールを使えばすべての関連情報を消化しやすい形式で提示することができます。
これにより多くの時間を節約し、BIツール利用者は他の業務に集中することができます。
第2に、利用者がより良い意思決定をするのに役立ちます。
すべての情報が1つの場所に集約されているため、傾向やパターンを発見しやすくなります。
これにより、BIツール利用者はより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができるようになります。
第3に、企業の課題の早期発見に役立ちます。
ビジネスにおいては、すでに発生した問題を解決することも大事ですが、問題が発生する前に発見することも大事です。
BIツールは様々なデータの関連性を分析し、人の目では気づかないような課題を発見することで、人が作業を行うよりも正確に、そして早く企業の課題を発見・解決まで導いてくれます。
BIのデメリット
BIツールの利用にはデメリットもあります。
まず、BIツールの導入にはいくらかのコストがかかります。
例えば、BIツールを動かすために必要なハードウェアやソフトウェアなどです。
さらに、BIツールの設定や使用には、ある程度の専門的な技術が必要であることから、想定したより多額のコストがかかってしまうこともあります。
第2に、BIツールは最大限に活用するのが難しいかもしれません。
BIツールを導入するためには、まず既存の社内システムデータをインポートし、連携作業を行うなどの手順が必要です。
さらに、ツール自体の使い方も複雑な場合があるため、BIツールの活用には導入からしばらく時間がかかるかもしれません。
第3に、BIツールは社内の望まない側面まで可視化してしまう可能性があります。
BIツールが提供するインサイトは業績や社内統制に良い影響を与える一方で、従業員にプレッシャーを与え、自分たちがあまりにも厳しく監視されているように感じさせるかもしれません。
BIの活用例
企業内の各部署におけるBIツールの活用例を紹介します。
営業部
営業担当者が顧客や販売数、業績などを把握し、営業効率を上げるのに役立ちます。
例えば、どの営業担当者がノルマを達成しているかというような情報をビジュアライズして表現することで、目立たせたい情報をより強調して表現することができます。
経理部
経理部門による財務状況の管理だけでなく、非経理部門のメンバーに財務状況を視覚的に説明する際にも役立ちます。
例えば、社内のどの部門が最もお金を使っているのかというような情報を、従来の表形式からさらにドリルダウンして詳細に分析していくことが可能です。
この情報は、どの部門でどの程度コストを削減できるかという戦略的な意思決定に利用することが可能です。
人事部
人事部門が従業員の情報を把握するのに役立ちます。
例えば、どの従業員のパフォーマンスが高く、どの従業員が改善を必要としているのかを視覚的に一目で確認することができます。
この情報は、人的資源をどこに配分するかという戦略的な意思決定に活用することができます。
BIツールの選ぶポイント
世の中にはたくさんのBIツールがあり、その中でも自社に合ったBIツールを選ばなければいけません。その基準を以下で説明します。
実行すべき分析
1つ目の要素は、どのような分析を必要としているかです。
BIツールの分析には、顧客のセグメンテーションから販売傾向の分析まで様々なバリエーションが存在します。
選択するツールが自社に必要な分析を過不足なく実行できることを確認してください。
必要な可視化
2つ目の要素は、行った分析をどのようなビジュアルで表現したいかです。
ビジュアライゼーションには棒グラフや円グラフ、クラスター分析やエクセルのような表形式まで様々なバリエーションがあり、選択するBIツールによってその得意分野も変わってきます。
選択するツールが自社に必要なビジュアライゼーションを作成できるかどうか確認してください。
使いやすさ
3つ目の要素は使いやすさです。
近年はセルフBIと呼ばれるユーザ自身が様々な角度から分析を行うことができるツールが一般的になっていますが、その分操作も複雑になっており、必要な情報を過不足なく引き出せるようになるまで時間がかかるかもしれません。
逆に、BIツールによっては限られた分析をごく簡単な操作で表現してくれるものもあります。
自社の目的や、実際に利用するユーザのスキルセットによって最適なBIツールを選択してください。
価格
4つ目の要素は、価格です。
各BIツールによって分析の得意分野は異なりますが、一般的に高価なツールほど機能が多くなります。
現在もしくは将来的に自社にとって必要な分析が可能であり、なおかつ予算内のものを選択してください。
市場にはさまざまなBIツールがあるので、自社に合ったものを見つけることが重要です。
BIツールを選択したら、利用者に使い方をトレーニングする必要があります。
トレーニングには時間がかかりますが、長い目で見ればそれだけの価値があるはずです。